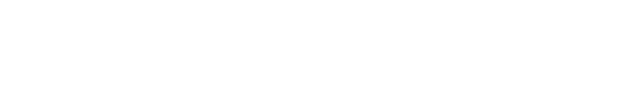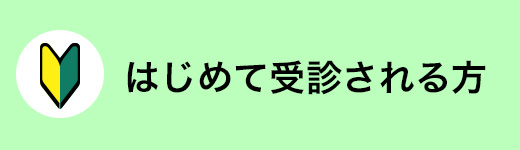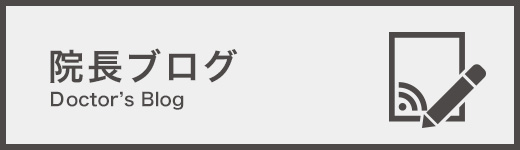頭痛治療の選択肢
薬物療法
市販薬による頭痛治療の基本
対象となる頭痛の種類
-
緊張型頭痛:市販薬の適応が最も多い
-
軽度~中等度の片頭痛:一部の市販薬が有効
-
群発頭痛・重度の片頭痛:市販薬は効果不十分(医療機関受診推奨)
主な市販薬の分類と特徴
| 分類 | 主成分 | 商品例 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|
| NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬) | イブプロフェン | イブA錠、ナロンエース、バファリンEXなど | 鎮痛・解熱・抗炎症。胃障害の副作用あり。 比較的片頭痛にも有効。 |
| ロキソプロフェン | ロキソニンSシリーズ | 病院処方薬と同成分。即効性あり。 空腹時服用は避ける。 |
|
| アスピリン | バファリンA、ケロリンなど | 歴史ある鎮痛薬。胃障害リスクや小児への使用制限あり。 | |
| アセトアミノフェン | アセトアミノフェン | タイレノールA、ノーシンピュアなど | 比較的副作用が少なく、妊婦・高齢者にも使用可。 ただし鎮痛効果はマイルド。 |
| 複合鎮痛薬 | 上記+無水カフェイン等 | ナロンエース、エキセドリンA、リングルアイビーなど | カフェインによる血管収縮効果が片頭痛に有効な場合あり。 過量使用に注意(MOHのリスク) |
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 月の使用回数 | 10回以上/月の服用で薬物乱用頭痛(MOH)のリスクあり。 |
| 胃腸障害 | NSAIDs使用時は空腹時を避け、胃薬併用が望ましい。 |
| 妊娠中の使用 | アセトアミノフェンは使用可、NSAIDsは妊娠後期で要注意。 |
| 肝障害・腎障害 | 長期連用は避ける。既往歴がある方は医師に相談を。 |
| 頭痛の性状確認 | 「今までと違う」「急に激しい」頭痛には市販薬を使わず受診を推奨。 |
市販薬では不十分な場合
以下のような症状がある場合、市販薬ではなく専門医の受診が必要です。
-
発熱・嘔吐・項部硬直を伴う頭痛(髄膜炎の疑い)
-
起床時や寝起きに悪化する頭痛(脳腫瘍・高血圧性・睡眠時無呼吸)
-
視覚異常、ろれつ障害、脱力を伴う(脳梗塞・脳出血など)
-
突然の激痛(くも膜下出血の可能性)
医師の処方薬
処方箋が必要な頭痛薬には、**市販薬では対応できない重度の頭痛(特に片頭痛や群発頭痛)**に使用されるものが多く含まれます。以下に代表的な薬剤とその特徴をまとめます。
【1】トリプタン系薬剤(片頭痛治療薬)
代表薬剤:スマトリプタン(イミグラン®)、ゾルミトリプタン(ゾーミッグ®)、リザトリプタン(マクサルト®)、エレトリプタン(レルパックス®)など
用途:発作時の片頭痛に対する即効性治療
特徴:
-
片頭痛発作時にできるだけ早く服用すると効果的
-
血管収縮作用があるため心疾患のある患者には注意が必要
【2】CGRP関連薬その他(片頭痛予防/発作治療)
代表薬剤:
-
予防薬:エムガルティ®(ガルカネズマブ)、アジョビ®(フレマネズマブ)、アイモビーグ®(エレヌマブ)
-
発作薬:レイボー®(ラスミジタン)、ウブレジー®(ウブロゲパント)※2025年日本未承認
特徴:
-
月1回の注射や定期内服で、片頭痛の頻度や強度を減らす
-
特にトリプタンが効かない、あるいは使えない患者に有用
-
高価だが、重症例では保険適用される場合もある
【3】鎮痛補助薬(処方薬に限定)
代表薬剤:
-
インドメタシン(インダシン®、インフリー®坐剤)
-
アセメタシン(ラーダメタ®坐剤など)
-
エルゴタミン製剤(クリアミン®Aなど、現在は使用頻度低)
用途:群発頭痛や、急性片頭痛に対する補助療法
特徴:
-
坐薬は嘔気が強い場合や経口困難な場合に有用
-
エルゴタミン製剤はトリプタン登場以前の主力薬
【4】予防薬(内服タイプ)
代表薬剤:
-
β遮断薬(プロプラノロールなど)
-
抗てんかん薬(バルプロ酸、トピラマートなど)
-
抗うつ薬(三環系:アミトリプチリンなど)
-
カルシウム拮抗薬(ロメリジンなど)
用途:片頭痛・緊張型頭痛の予防
特徴:
-
継続的に服用し、発作の頻度や重症度を低下させる
-
患者の基礎疾患や副作用リスクに応じて選択
【補足】市販薬では対応困難なケース
-
月に4回以上の片頭痛発作
-
日常生活に支障をきたすほどの痛み
-
嘔吐を伴い内服できない
-
市販薬が無効
→ このような場合は、専門医による評価と処方薬の導入が推奨されます。
非薬物療法
非薬物療法は、薬物の副作用を避けたい患者や、薬物療法だけでは不十分な場合に重要な補完手段です。主に以下の6カテゴリーに分けられます:
1. ライフスタイルの改善
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 睡眠 | 規則正しい睡眠(就寝・起床時間の一定化) |
| 食事 | 低血糖予防、トリガー食品(チーズ、赤ワインなど)の回避 |
| 水分摂取 | 脱水を防ぐ(特に片頭痛では重要) |
| 運動 | 有酸素運動(例:ウォーキング、ヨガ)は緊張型頭痛や片頭痛を予防 |
| 姿勢 | PC作業時の首肩負担の軽減(エルゴノミクス) |
2. 認知行動療法(CBT)
- 効果:ストレス関連の片頭痛や緊張型頭痛に有効
- 内容:
- 自動思考の見直し
- 対処スキルの獲得
- 行動パターンの修正
- 実施方法:心理士との面談、またはオンラインCBTなど
3. バイオフィードバック療法
- 仕組み:皮膚温や筋電図をリアルタイムで可視化し、自己制御力を高める
- 効果:特に筋緊張型頭痛や片頭痛の予防に有用
- 種類:筋電図フィードバック、皮膚温フィードバックなど
4. リラクゼーション療法
| 種類 | 方法 |
|---|---|
| 漸進的筋弛緩法(PMR) | 各筋群を意識的に緊張・弛緩させる |
| 呼吸法 | 腹式呼吸や4-7-8呼吸法 |
| 瞑想・マインドフルネス | 注意を今に向ける訓練(ストレス軽減に有効) |
5. 理学療法・徒手療法
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 理学療法 | 頸部や肩甲帯の可動域改善、筋力トレーニング |
| マッサージ・指圧 | 筋緊張の軽減(特に緊張型頭痛) |
| 鍼灸 | WHOも片頭痛への適応を認めており、有効性が報告されている |
6. 神経調節・補助的技術
| 技術 | 説明 |
|---|---|
| 経皮的電気神経刺激(TENS) | 頭部や頸部に装着する機器で痛み信号を抑制 |
| 頭皮冷却・温罨法 | トリガーポイントや血管反応に作用 |
| デジタルヘルスツール | 頭痛日記アプリやウェアラブルで発作予測と管理 |
実臨床での活用のポイント
- 患者教育が不可欠:非薬物療法の継続には本人の理解とモチベーションが重要
- 組み合わせが効果的:薬物治療との併用が望ましい(予防薬+CBTなど)
- 個別化:頭痛のタイプ・背景・ライフスタイルに応じた選択を