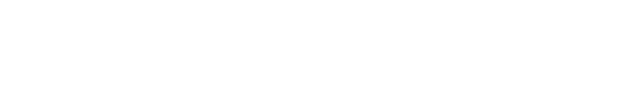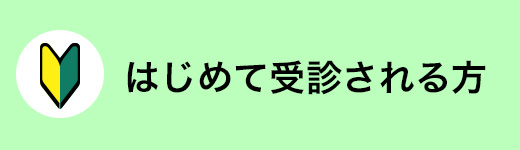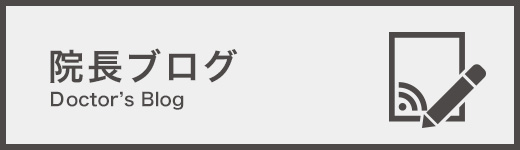スマホと頭痛——何が起きている?どう対策する?
「スマホを見ると頭が重い」「夕方になるとこめかみがズキズキする」——そんなご相談を毎日のようにいただきます。ポイントは、“スマホそのものが毒”なのではなく、使い方(時間・姿勢・タイミング)が頭痛を引き起こす条件をそろえてしまう、ということです。原因と具体策をわかりやすく解説します。
1) 目の疲れ(デジタル眼精疲労)が引き金に
スマホ画面を凝視すると、まばたきが減ってドライアイ傾向になり、焦点調節の負担も増えます。これが前頭部や目の奥の痛みにつながります。大規模レビューでは、デジタル眼精疲労は確かに存在し、いわゆるブルーライトカット眼鏡は少なくとも短期では症状軽減の決め手にならないと結論づけられています。
今日からできる対策
・画面を30–40cm以上離す/文字サイズを大きくする
・20-20-20ルール(20分見たら20秒、6m先を見る)
2) 首(うなじ)・肩のこりから来る頭痛(“スマホ首”)
うつむき姿勢が続くと、頭の重さが首に倍々ゲームでかかります。系統的レビューでは、成人では“前方頭位(うつむき姿勢)”と頸部痛の関連が有意で、これが後頭部〜側頭部の緊張型頭痛を悪化させます。
今日からできる対策
・目線の高さにスマホ(胸元ではなく顔の前へ)
・あごを軽く引く+肩を後ろに引いて耳・肩・骨盤を一直線に
・1時間に1回、首の可動域ストレッチと肩甲骨まわしを30秒
3) 夜の使い過ぎは良質の睡眠を妨げ、翌日の片頭痛を招く
夜の強い光は体内時計を遅らせ、メラトニン分泌を抑えて寝つきの悪さ・睡眠の浅さにつながります。就寝前の明るい画面を減らす/通知を切ることは、翌日の頭痛予防に直結します。ヒトにおける試験では、夕方の強い青色光を減らすとメラトニンの立ち上がりが早まることが示されています。ただし「ブルーライトカット眼鏡=頭痛予防の特効薬」ではありません。まずは光量とタイミングの調整が本丸です。
今日からできる対策
・就寝1–2時間前は画面の断捨離:明るさ自動調整+ダークモード
・通知をサイレントにして脳を興奮させない
・寝室は間接照明・低色温度へ(天井直当ての白色LEDは避ける)
4) 時間の長さそのものもリスク
小児・若年では、長時間のスクリーン使用と頭痛の関連が報告されています(片頭痛持ちの一部で顕著)。成人の前向き研究でも、モバイル端末の多用と頭痛の関連が示唆されます。連続時間を区切ることが鍵です。
今日からできる対策
・1回のスマホ使用は最長30–45分と決め、アラームで区切る
・通勤や待ち時間は音声入力や耳で聴く(首を下げない)
・屋外の自然光に毎日15–30分は当たる(体内時計のリセット)
5) 片頭痛もちの方こそトリガー管理を
片頭痛は複数の小さな誘因の合算で発作に到達します。スマホ関連では、
・まぶしい点光源(暗い部屋での明るい画面)
・睡眠リズムの乱れ(夜更かし・寝坊)
・首こり・肩こり(長時間うつむき)
が足し算になります。頭痛ダイアリーに「使った時間・姿勢・就寝前の使用有無」を残すと、ご自身の“閾値”が見つかります。当院でも急性期薬+生活調整+予防薬/CGRP関連治療を組み合わせ、個別最適化を行います。
当院おすすめ“スマホ×頭痛”チェックリスト
-
画面は顔から30–40cm以上/文字は大きめ
-
20-20-20で焦点リセット
-
スマホは目線の高さ、あごを軽く引く
-
45分使ったら3分休憩——立って肩甲骨を動かす
-
就寝1–2時間前は使わない/通知オフ
-
頭痛ダイアリーで**“使い方と頭痛”の相関**を記録
-
痛みが増える、生活に支障が出る場合は専門医へ
赤坂おかだ頭痛クリニックでは、使い方の修正だけで痛みがグッと軽くなるケースを多く経験します。自己流で改善しない場合は、お気軽にご相談ください。生活調整・薬物療法・CGRP関連治療など、患者さんに合わせて一緒に最適解を探します。